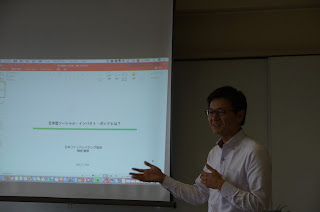NPO交流一杯の会~社会福祉法人あむ林健一さん、小竹徹さんをむかえて

今回の一杯の会は、障がい福祉サービスを展開している社会福祉法人あむの林さんと小竹さんをお迎えします。 2018 年 1 月 19 日 ( 金 )18 : 30 ~ 20 : 30 社会福祉法人あむについて 『あむ』という名称は、編む、結び目をつくりたいとの願いをこめて、スタッフ全員で決めました。障がいのある人もない人もおとなも子どもも、尊び合い、学び合い、助け合いながら暮らせる社会をめざして、ご近所を含めさまざまな<出会い>からつながりを編み、<結び目>をつくりたい。そんな思いを持って私たちは活動しています。 ゲストスピーカー 林健一さん 林 健一さん44歳。ワン・オールセンター長。家族構成 妻 娘。趣味はディズニーランド、キン肉マン。 小竹 徹さん42歳。ワン・オール 相談支援専門員。家族構成 妻 息子。趣味はキャンプやスキー。 ・あむの事業 【障がい福祉サービス】 ばでぃ(居宅介護事業所)、に・こ・ぱ(児童発達支援・放課後デイ)、びーと(生活介護)、こまち(共同生活援助)、相談室にっと(指定特定・一般・障害児相談支援)、相談室ぽぽ(委託相談)、ワン・オール(基幹相談) 【ワンマイルネット事業】 ご近所ネットワークの構築 ● 参加費/ 500 円 小竹徹さん ● 場所/市民活動プラザ星園内 ● 定員/ 20 人程度 ●お申込み・お問合せ/ NPO 推進北海道会議 メール info@hnposc.net TEL : 011-200-0973 FAX : 011-200-0974